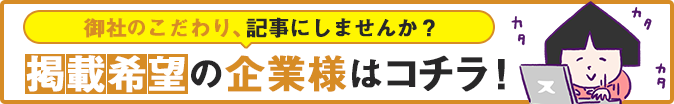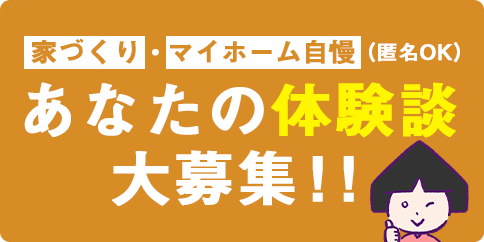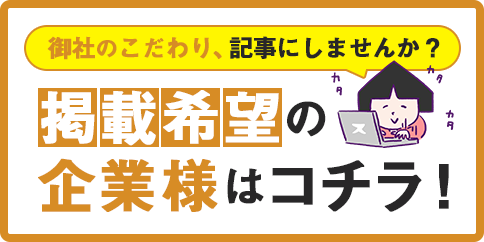「どっちがお得?」に惑わされるな!【元金均等返済 / 元利均等返済】目的別で選択!

以前【家づくりの流れ3STEP】でおおまかな流れを紹介。
【住宅展示場】や【見学会】に行く前にこの3STEPを踏むべし。
理由と詳細はこちらをチェック▼以前紹介した【家づくり3STEP】はこちら▼
家づくりの流れ
1..お金のこと
2..建物のこと
3..土地のこと
『“とりあえず”と住宅展示場とかに行くのはナッティン(無し)ということか!』
『自分達家族の身の丈を知らずして、家づくりは進まぬ、ということか!』
この1.2.3の流れが見えてきたところで【お金のこと】で『スミ子式|家計の見直し』を紹介しました。
↑ここで例に挙げた家族の支払可能額・年支払可能額が計算できた!
この“情報という武器”を手に我々のこれからの目標は…【住宅ローンシュミレーション】
目次
目指せ【住宅ローンローンシミュレーション】!

金利 を知り
↓
変動金利・固定金利 を知り
↓
元金均等・元利均等 を知り
↓
団信 を知る
↓
意味の分かった状態で【住宅ローンシミュレーション】に挑む!
『収入+支出額』と『自分達が月々住宅ローンにどの程度の金額を充てられるか』が分かれば、『組める住宅ローン』の金額をシュミレーションできる。
組める住宅ローンの金額が分かって初めて、【土地のこと】【建物のこと】がリアルに考えられるよ!
スミ子のお金の教室
1限目:【金利】について
・金利ッテナニ?
・1.0%違うといくらくらいの違い?
・高いから悪、安いから善!ってわけじゃない!
2限目:【変動金利・固定金利】について
1. 全期間固定金利型
2. 変動金利型
3. 固定金利期間選択型
ここまでやってきました。
金利 を知った
↓
変動金利・固定金利 を知った
↓
元金均等・元利均等 を知り
↓
団信 を知る
↓
意味の分かった状態で【住宅ローンシミュレーション】に挑む!
【金利を知った】【変動金利・固定金利 を知った】
お次は【元金均等・元利均等 を知る】
ここがマスターできればいよいよ【住宅ローンシミュレーション】ができる!
シミュレーションはいつでもできるんだけど、金利について理解していないと正しい数値を出すことはできないので、やっても意味ないよね。
「元利均等返済」と「元金均等返済」
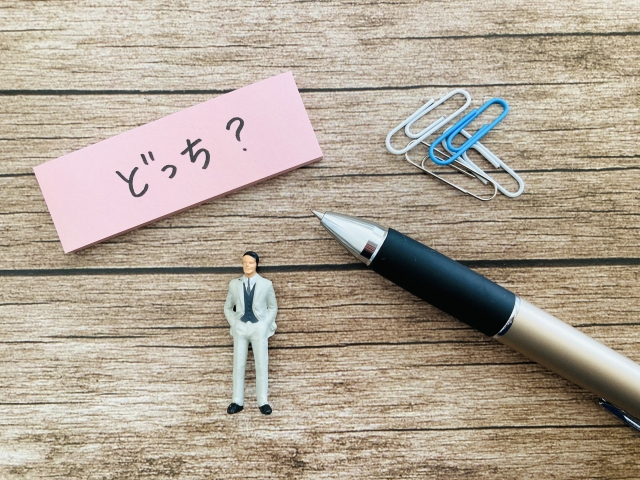
住宅ローンの返済方法には、毎月返済額が変わらない「元利均等返済」と、毎月返済額のうち元金分(借金返済に充てられる分)が同じで徐々に毎月返済額は減っていく「元金均等返済」の2つがある。
元利均等返済=毎月の返済額はずっと同じ金額。
元金均等返済=毎月の返済額が少しずつ低くなる。
※元金均等返済の方が、元金の返済が早く進むため総返済金額は少なくなる。
現在の超低金利時代が続く限り総返済額に大差はなく、将来の生活設計の立てやすさから「元利均等返済」がおすすめ。
「元利均等返済」と「元金均等返済」は一字違いで、間違いそうになるが、毎月返済額の計算方法が大きく異なる。
元利均等返済とは

「元利均等返済」は、元金分と利息を合わせた毎月の返済額が変わらないので分かりやすい。
ただし、毎月返済額に占める元金分と利息の割合は毎月変わる。
返済が進むほど元金分の割合が増えていくためで、最初は借入残高がなかなか減らない。
「元利均等返済」は毎月の返済額が同じなので、将来の生活設計が立てやすいというメリットがある。
しかし、返済期間が同じ場合、「元金均等返済」より総返済額が多くなるというデメリットも。
え
元金均等返済とは

一方、「元金均等返済」は毎月返済額が徐々に減っていく。
同じなのは毎月返済額のうち、元金分だ。返済期間35年の場合、借入額を420カ月(35年×12カ月)で割れば、毎月の元金分の返済額が出る。
利息は借入残高に金利を掛けて計算する。
銀行の表示する金利は年利なので、毎月の金利は年利÷12で計算する。返済額は元金分+利息となる。
当初の毎月返済額は「元利均等返済」より多くなるが、毎回の返済で借入残高が減るにつれて利息も減っていくので、毎月返済額は次第に減っていく。
返済期間が同じ場合、「元金均等返済」は元金の返済が「元利均等返済」より早く進み、総返済額も少なくなるのがメリットだ。
しかし、当初の返済額が「元利均等返済」より多くなるというデメリットがある。
返済シミュレーションを比較|返済額の差はどのくらい?
 例えば35年ローンで組んだ場合
例えば35年ローンで組んだ場合
●元利均等返済は毎月の支払総額は35年間変わらない。
<参考>
例として毎月8万支払いだとすると最初は元金6万利息2万となりますが、最後は元金5.5万利息0.5万のように、割り算して利息を先に返していくような返済方法になる。
この返済方法は少し割高にはなるけど、支払いに変化が無いので生活が安定し、計算しやすい。
●元金均等返済の場合は年数経過毎に支払額は少なくなる。
<参考>
例として元金毎月7万固定+利息(初年度4万→34年後0.5万)のようになる。
これは元金を35年間で均等に割って支払っていくことで、元金はどんどん減るから、その分乗っかる利息も減っていく事ということ。
なので、元金がある程度減るまでの数年は負担が大きい。
選択基準ってなに?
 どちらを選んだ方がいいかは、現在の家計や将来の生活設計によって違ってくる。
どちらを選んだ方がいいかは、現在の家計や将来の生活設計によって違ってくる。
公務員など、将来の収入がある程度見通せる人なら、「元利均等返済」の方が家計の管理はしやすい。
一方、今は夫婦共働きだが、子供ができたら妻が退職する予定だというような人は、家計に余裕があるうちに元金を減らせる「元金均等返済」がおすすめ。
ただし、これは普通の金利状態のときの話。
金利が1%を切っている現状では、総返済額に大差はないので、元金均等返済のメリットはほとんどない。
むしろ、元利均等返済で返済額を一定にし、将来の生活設計を立てやすくすることのメリットが上回る。
実際、金利0.5%(35年固定金利)とし、両者を比べてみよう(借入額3000万円、借入期間35年と設定)
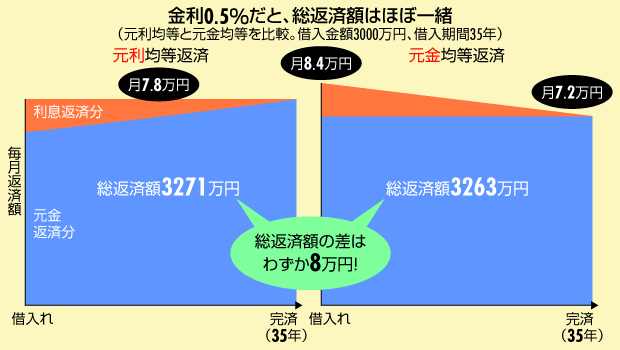 (引用:ダイヤモンド不動産研究所)
(引用:ダイヤモンド不動産研究所)
「元利均等返済」は総返済額が3271万円で、毎月返済額はずっと7.8万円。
一方の、「元金均等返済」は、総返済額が3263万円で、毎月返済額は最初8.4万円だが、徐々に減少していき、420カ月目は7.2万円になる。
それぞれの図の面積が総返済額にあたるのだが、こうして比べてみると面積はほとんど一緒。
「元利均等返済」は総返済額がわずかに8万円高いだけであり、一方で返済額が変化しないというメリットに変わりはない。
繰り上げ返済を考えてみる
 「元利均等返済」「元金均等返済」を考えるうえで、“繰り上げ返済”が顔を出すことがある。
「元利均等返済」「元金均等返済」を考えるうえで、“繰り上げ返済”が顔を出すことがある。
繰り上げ返済検討してみる
住宅ローンの総返済額を少なくしたいのであれば、実は「元利均等返済」「元金均等返済」という返済方式にこだわるよりも計画的な繰り上げ返済を行うほうが影響が大きくなる。
というもの。
以下の表は、元利均等返済で借入から10年後に150万円の繰り上げ返済を行った場合と、元金均等返済で繰り上げ返済なしの場合の総返済額を比較したもの。
| 元金均等返済で繰り上げ返済なしの場合の総返済額を比較 |
| 毎月の返済額 ※元金均等返済は初月の返済額 |
総返済額 ※諸費用は含めない |
|
|---|---|---|
| 元利均等返済 (10年後に150万円の繰り上げ返済) |
10万2,817円 | 3,653万8,623円 |
| 元金均等返済 (繰り上げ返済なし) |
10万7,500円 | 3,654万3,150円 |
| 差額 | ▲4,683円 | ▲4,527円 |
この表では、元利均等返済で繰り上げ返済を行ったほうが総返済額が少なくなってる。
つまり、返済方式による総返済額の差は、繰り上げ返済をすることで変わってくるということ。
もちろん元金均等返済で繰り上げ返済を行えばさらに利息負担は少なくなるが、元金均等返済では変動金利の125%ルールが適用されない等のデメリットも存在するのも事実。
繰り上げ返済、否定してみる
住宅ローンは数十年に渡って返済していくが、「なるべく早く完済したい」「月々の返済額を減らしたい」と考える人も多いはず。
人によっては「元利均等返済」で繰り上げ返済を行ったほうが総返済額が少なくなる、と進める人もいる。
繰り上げ返済の方法には「期間短縮型」と「返済額軽減型」の2種類がある。
期間短縮型は、月々の返済金額は変えずに返済期間を短くする返済方法。
一方、返済額軽減型は、返済期間はそのままで月々の返済金額を減らす返済方法。
この場合は、繰り上げ返済額を月々の返済額に均等に充当することになります。

繰り上げ返済のデメリットはこいつら!
金利が低く利息が軽減される効果が薄い
低金利で住宅ローンを組んだ方は繰り上げ返済をしてもひと昔のように大きく利息が軽減されるわけではないため、積極的に繰り上げ返済をしなくても良い。
。
住宅ローン控除額が減額される可能性がある
繰り上げ返済をすると、住宅ローン控除額が減額になってしまう可能性がある。
住宅ローン控除は、住宅ローンを利用して自宅を購入した場合に、一定の条件を満たすと年末の住宅ローンの残高に応じて、所得税や住民税から控除される減税制度。
団信の保険金額が減ってしまう
繰り上げ返済をすると、団信の保険金額が減ってしまう。
団信とは団体信用生命保険の略であり、住宅ローンの返済中に万が一契約者が亡くなってしまった場合、保険金により残りの住宅ローンを完済できる生命保険。
団信の保険金額は住宅ローンの残高と同額。
全額繰り上げ返済後にがんになってしまっても、団信からの保険金はおりないため、繰り上げ返済のお金で治療費に充てられたかもしれないと後悔することもあるかも。
団信に加入しているのなら、万が一のときのために繰り上げ返済をせず、手元資金を残しておくのもひとつの考え。
急な出費やライフイベントに対応できなくなる
未来は何が起こるか誰にも分からない。
子どもが留学をしたいと言い出すかもしれませんし、車が故障してすぐに買い替えなければならないことも。
怪我や病気で高い治療費がかかる場合もある。
コロナの流行があったので、急に収入が減ってしまうことも想像できるのでは?退職に追い込まれる、ということも多かったからね。
繰り上げ返済をすることで手元資金が減少し、急な出費やライフイベントに対応できなくなってしまう場合がある。
現段階で繰り上げ返済をすべきなのか判断できるようライフプランを立て、今後の必要金額や急な出費に備えた資金を確保したうえで繰り上げ返済を検討することが大切。
繰り上げ返済するぐらいなら資産運用できる?
住宅ローン返済中に、まとまったお金が用意できた場合、繰り上げ返済を行うか、資産運用するか、迷っている人も多い。繰り上げ返済を行うことで、利息軽減により総返済額の削減効果を得られるが、それよりそのお金を長期に資産運用にまわすことのほうが得策となる可能性もある。
「元金均等返済と元金均等返済はどちらの返済方式がお得なのか」という議論も多くあるけど、繰り上げ返済を想定しない場合の総返済額での比較では元金均等返済方式がややお得になる。
ただし、利息負担の損得だけで判断するのではなく、それぞれの返済方式では特徴が異なるため、メリットやデメリットを理解した上でご自身のライフスタイルに合わせて選びたいね。
スミコに相談する
※掲載している情報は公開時点の情報です。最新の情報は各メーカー公式サイトよりご確認ください。
記事検索
プロフィール

新潟スミコ
アラサー主婦。
サラリーマンパパと2児の子育て奮闘&エンジョイ中
新潟生まれ新潟育ちで趣味はマイホーム情報収集・住宅見学
産後、マイホームの夢が膨らみ住まいづくり情報収集してたら【家ヲタク】に!同じ悩みを持つ新潟県民に向けて役立つ【住まいづくり情報】を発信!